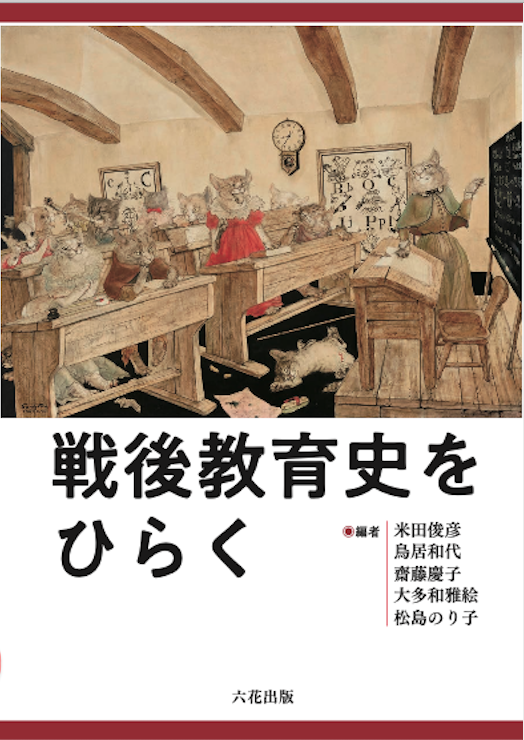
2025年、日本社会は「戦後80年」を迎える。近現代教育史において1872(明治5)年~1945(昭和20)年8月を「戦前」とするなら74年間である。われわれはすでに、時間的には「戦前」を超える厚みもった「現在」に生きている。では、「明治期」や「大正期」、「昭和戦前期」として思う描く教育史像に対し、「戦後」の教育史像は確立されているだろうか。近年、日本教育史研究者の間でも、教育学の他領域に比して研究蓄積の乏しさが自覚されつつある。2022年の『1950年代教育史の研究』(野間教育研究所紀要第64集)発刊、2024年8月の日本教育史研究会サマーセミナーの「戦後教育における1950年代とは」というテーマ設定、そして2024年11月に発刊された米田俊彦・鳥居和代・齋藤慶子・大多和雅恵・松島のり子『戦後教育史をひらく』(六花出版)では11篇が1940~60年代を対象とした論文で構成される、といった取り組みが続いている。
本演習では、これら「開拓的」な研究が試みられつつある状況に学び、1950年代の教育史像とは何か、そしてその後に続く(また現在にも接続する)「戦後教育史像」とは何かを考えていくこととしたい。
本演習では、これら「開拓的」な研究が試みられつつある状況に学び、1950年代の教育史像とは何か、そしてその後に続く(また現在にも接続する)「戦後教育史像」とは何かを考えていくこととしたい。
